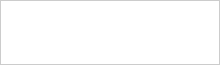2025年4月4日
第6回ジェロナグーラ便り
ジェロナグーラ大学
小 山 良 夫
■春真っ盛りのポーランド:
-アパートの前に2本立っている薄桃色のつぼみの付いた大きな木が、ずっと何の木か分からなかったのですが、最近花が咲き始めてそれが桜の木だったことが分かりました。小さな花がたくさん付いているのですが、よく見ると5弁の小さな桜の花なんです。日本の桜と比べると花があまりに小さいし、葉も木の幹も日本の桜のようじゃありません。しかし一旦桜だと分かると急に親しみが湧いて、時々写真を撮ったりしています。人は国が変わると姿かたちが変わりますが、桜も場所が変わると見目も違うのだろうと、何となく勝手に納得しています。
-3月30日に夏時間に移行して、時計の針を1時間進めました。ついこの前まで授業の開始時間が薄暗かったのがウソのようです。皆教室に入ってくると「こんにちは」と挨拶し、だれも「こんばんは」という者はいなくなりました。
-最近日本語クラスの学生の中で、日本に2週間とか、1カ月とか旅行するものが何組か出てきました。そのために日本語の授業を大分継続して休むことになるので、帰って来てから追いつくのに大変だぞとこちらは勝手に心配していますが、彼らは嬉々として日本に行くことを楽しげに語り、見どころなど気軽に聞いてきます。沖縄にしばらく滞在するというカップルがいたので、私は自分の昔の経験を元にアドバイスをしました。
■日本語の授業及び関連活動の状況:
-夏期セメスターの授業は3月4日から始まり、6月19日に修了の予定です。夏期セメスターは全部で15週あり、これまでに3月初めから4月1週目までの計5週間の授業を終了した時点で、常時出席者がほぼ固まってきました。出席優秀者は5クラス合計で約35人おり、この他に10名ほどが頑張ってもう少し出席率を上げれば、最終日には3分の2の出席を条件としている、年間日本語コース修了証書を受け取れそうです。
-ここまで、1年間の全過程30週のうち20週を終了した訳ですが、やはり熱心に授業に出て、毎回の宿題もきちんと提出している生徒は、週一回という超スローの授業にもかかわらず日本語の上達が着実であり、今後も学習を続けて行く下地ができてると言えます。他方で授業を時々休み、宿題もあまり熱心に提出しない生徒は、例えドロップアウトしなくとも、授業中の反応が鈍く、学習の積み上げができていないのが一目瞭然です。語学は地道な努力の継続であるということが、ここにはっきりと現われています。
-隔週1回のペースで実施している「Japanese Club」は、本セメスターに入って3月19日(水)と4月2日(水)の2回実施しました。トピックは「俳句」でした。最近は英語や他の国の言葉の俳句も盛んなようですが、私は日本の俳句にこだわって紹介することにしました。対象がせっかく日本語を学習している生徒なので、日本語学習の一環としても、俳句の5・7・5のリズムを体感してもらいたいと考えたからです。次に俳句には季語を入れる必要がありますが、手持ちの歳時記の春の部分や、オンラインの春の季語をコピーしたりして皆に季語を理解してもらい、次に自分の気に入った春の季語を選んでもらいました。詳細は省略しますが、最終的に、参加者全員に自作の日本語の俳句を2句づつ作ってもらいました。そして、これらを基に教室内でミニ句会を開いて、皆で良い句を投票で選んで感想を述べあうなど、短時間でしたが結構楽しい時間でした。
-3月29日(土)に、ワルシャワの日本大使館広報文化班で、第43回日本語弁論大会があり、私の日本語コースの学生(高校生)が一人出場しました。私も付き添いで久しぶりにワルシャワに2泊3日で滞在しました。日本語弁論大会には全部で19名の参加者があり、ほとんどは国立大学の日本語学科の学生でしたが、私の生徒は唯一高校生で参加し、残念ながら入賞は逃しましたが大変良いスピーチをして、審査員の評価も高かったと聞いています。翌日の日曜日、ついでにワルシャワ大学日本学部で開かれたポーランド日本語教師会の会合にも顔を出すことができました。
■日本語教師連絡会:
-4月4日(金)10時より、第6回目の日本語教師連絡会をオンラインで開催しました。今回は既に2名の派遣者が帰国しており、その後任として来週派遣される予定の教師が日本から参加して、参加者は全員で7名でした。
-それぞれの教師の日本語教育の現状について、既に任期の3分の2が終了した時点での報告がなされました。赴任地の状況に応じて、日本語教育が主体のところと日本文化の紹介が多いところとの活動の違いがかなり出てきていますが、それぞれの赴任先の特徴を生かした活動が軌道に乗っています。また、少しづつですが教師間の相互訪問やイベントへの相互協力等も行われ始めました。