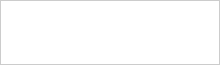12月半ば、ついに聖キリル・メトディウス大学(スコピエ)に来ることができました。到着した翌日からJapanese language 1 (にほんご1) のクラスがあり、大学で授業を実施しました。はじめの一週間は、外国人の滞在関連手続きやスマホのSIMカード開通手続きで忙しかったです。授業は選択科目が月・水・金、課外授業が月・火です。木曜日は人事課の職員さんと一緒に関係省庁に出向きましたので、1週目は毎日大学に行っていたことになります。おかげさまで、大学講師寮から大学キャンパスまでの道はよく覚えられました。それと、言語学部・哲学部の大学キャンパスは迷路のようでしたが、2回目、3回目でようやく自分自身で教室に行ったり私の事務所に行ったりすることができました。
それにしても、慣れない手続きというものは想像以上に大変で、北マケドニアではID番号なしで通信関係契約をどのように確保するかが初めの障壁となりました。他の外国語講師たちにもいろいろとアドバイスを得ながら、街の大きなモール内の確実に店員がいるところに行き、その会社のプリペイドSIMにTopupして、スマホのホットスポット機能を利用してPCに繋いでいます。一応、これで何とか外でもインターネットに接続できる環境は得られました。いやはや、授業をしていた方がはるかに気楽です。
12月の言語学部のイベントとして、12月19日、学部の名前になっているブラジェ・コネスキ(Blaze Koneski)の誕生日のAssemblyがありました。前回レポートではブレイズと英語読みをしていましたが、マケドニア語では「ブラジェ」と読みますので、読み方を「ブラジェ・コネスキ」と改めます。ブラジェ・コネスキは、マケドニアの著名な詩人、散文家、エッセイスト、言語学者、文学史学者、翻訳家であり、マケドニア言語の規範を確立した一人です(Koteva & Celik, 2021)。光栄にも参加のお誘いをいただき、はじめから終わりまで参加してきました。言語学部の学生たちがブラジェ・コネスキの作品、詩を読み上げ、ギター演奏などもありました。ほとんどマケドニア語で詩の内容を理解することはできませんでしたが、厳粛な雰囲気と彼への敬意を感じることができました。

ブラジェ・コネスキの銅像 
Assembly会場
さて、授業報告です。正規の選択科目は対面授業に切り替えました。課外授業はいろんな学部から参加者がいるため、学内の講師オフィスからオンラインで実施しています。
1. 選択科目
(1) Japanese language 1(にほんご1)
使用教材: まるごと 入門A1 かつどう・りかい
対面授業でアクティブな雰囲気です。学生の表情を見ながら、みんなで発話をすると臨場感がでます。第5課の後半まで進んでいますが、残りの授業で第6課までは終える予定です。文字学習に関しては、今期はひらがなと教科書に出てきた漢字(6つ)に限定して習得してもらいます。まるごとA1のりかい第1課でひらがな、第2課でカタカナを学ぶことになっていますが、カタカナは学生にとってどうしても覚えにくく難しいので、学習負担を考慮し、ローマ字に置き換えてもよいことにしています。しかし、カリキュラム上、先生と学生で文字を一緒に2行ずつ書くような時間がゆっくり取れないため、いつ、どこで、どのように習得したらいいかは今後の課題です。
(2) Japanese language 3(にほんご3)
使用教材: まるごと 初級A2-1 かつどう・りかい
動詞テ形や形容詞の接続がでてきますが、学生たちはよく理解しています。対面授業だと活用ルールを板書して示して、そのまま残しておき、学生たちはいつでも物理的に参照できることが一つの利点です。また、『まるごと』の教科書の巻末資料にも文法まとめが載っているので、本課を進めながら、全体のテ形活用ルールの中での位置づけを間髪入れずに直接示せるのはとても教えやすいです。授業も円滑に進みますし、学生達も巻末資料の存在をはじめて知り、教科書自体を使いこなすための第一歩になります。Japanese language 3の授業も第5課に入っていますが、トピックとしてキリがいい第6課までは終えたいところです。第6課は道案内のテーマなのでスコピエのリアルな建物名を使って授業する予定です。
2. Extracurricular course (課外授業)
使用教材: いろどりA1
教科書選定に関して、オンライン授業での使用、また、授業資料共有に関して著作権法上の問題をクリアしている『いろどりA1』を採用しました(いろどり「利用上のルール」Q23-A23; Q28-A28)。課外授業なので、日本語にふれること、日本語学習を楽しむことに重点を置き、『いろどり』以外にも『エリンが挑戦!にほんごできます』のビデオを見たり、『まるごと』の文化紹介のビデオも見たり、フレキシブルな感じで自由に授業しています。北マケドニアでも日本のアニメとゲームは絶大な知名度があります。学生たちはいろんなアニメを本当によく知っています。ポーランドにいたときと比べると、学生達から出てくるアニメの名前とその傾向がなんとなく少し違うかなと個人的に思っていますが、興味深く学生達の話を聞いています。

アレキサンダー大王像とクリスマス装飾 
アレキサンダー大王とクリスマスツリー 
サンタのストッキング
スコピエ市街でもアレキサンダー大王像の周辺はクリスマスの飾りが増えてきて賑やかになってきました!Clove入りのホットワインがあったら、ぜひ堪能したいものです。
小林
References:
The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa. (n.d.). FAQ – Terms of use.
https://www.irodori.jpf.go.jp/en/faq.html
Koteva, I., & Celik, M. (2021). ANALYSIS OF THE POETRY “THE DIFFICULT” BY BLAZE KONESKI. PALIMPSEST/ПАЛИМПСЕСТ, 6(12), 117-124.