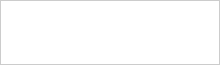10月報告
9月12日(月)にソフィア空港から入国し、13日(火)にヴェリコ・タルノヴォに到着した。16年前(2007年)に一度訪れてはいるものの、全く異なる新鮮さを感じながらのスタートとなる。バスが発着するアフトガーラ・ユグでK先生の出迎えを受ける。今日からこの街が僕の街になると思いながらバスに揺られる。ヴェリコ・タルノヴォはバルカン山脈の麓に位置する。歴史は古く第2ブルガリア帝国の首都でもあった。現在は人口7万人の地方都市。週末には多くの観光客が訪れる。蛇行するヤントラ川が深く削り取った斜面に家々が階段状に建てられている。それが西陽を受けて赤く染まったときの眺めはひときわ美しい。大学は市内東部のスヴェタ・ゴラの丘の中ほどに建つ。大学からの眺めも美しく、谷向こうのツァレベツの丘に教会と長く続く城壁が見える。これほど眺めのいい大学を私は知らない。けれど、その眺めのすばらしさはこの大学の魅力の一部でしかないのであろう。
今回は、授業と寮の部屋とビザ受領について報告する。
1 授業の概要について
1)日本語学科は1年生~4年生までの4クラス
内訳は1年20名・2年18名・3年14名・4年18名。
2)担当スタッフは4名(5名)
ブルガリア人女性3名と日本人ボランティア。今年度は休職中(出版準備活動中)の女性もいらっしゃる。日本語堪能な先生方は気さくで仲がよく、十分なコミュニケーションがとれていると感じられる。
3)授業期間
前期 9/19~1/7 その後テスト期間(1/9~1/27)
クリスマス休暇は12/24~1/2 冬休み1/28~2/19
後期 2/20~6/3 その後テスト期間(6/5~6/23)
4)日本語センターは職員準備室
室内には7300冊の蔵書(日本語記載)がある。詳しくは次回以降の報告に譲る。
5)持ち時数は週3・5時間 + カウンセリング1時間
4年生の授業は隔週で実施しているため3・5時間となる。カウンセリングの時間は準備室にいて、主に図書の貸し出しを行ったり、学生の相談にのったりする。持ち時数が少なく、しかも授業は月~水曜日で終わるので、授業開始1か月後から1年生「会話」の時間(火曜日、希望制)を設けた。
6)授業時間は1h45。ただし、途中休憩を取らない場合は1h30。
1限 8:15~10:00
2限 10:15~12:00
3限 12:15~14:00
4限 14:15~16:00
5限 16:15~18:00
7)使用テキスト
『みんなの日本語 初版版』『翻訳・文法解説』(全学年)
『書いて覚える文型練習帳』『聴解タスク』『初級で読めるトピック25』(1・2年生)
これらのテキストを使って、週あたり1年7時間・2年5時間・3年2時間・4年3・5時間学習する。上級生には「翻訳」「通訳」等の専門科目がある。
7)授業の進め方
『みんなの日本語』を毎時間リレーするような形で進める。あらかじめ予定は組まれているが、前の担当者が終了したところから次の担当者は授業を始める。よって担当者間の引き継ぎ・連絡は欠かせない。これがスタッフのコミュニケーションのベースになっているように感じる。ただし、授業計画は日本人ボランティアが「文法」にならないように配慮されている。
8)学生の印象
明るく素直で接しやすい。とても優秀で学習には熱心に取り組む。授業中には比較的よく質問したり発言したりする。3・4年生の中には仕事(アルバイトではなくて)をしている学生もいて、授業は欠席がちである。
2 授業の進度について(11/9現在 新年度開始から8週間目)
1年生 『みんなの日本語初級Ⅰ』第9課
2年生 『みんなの日本語初級Ⅱ』第43課
3年生 『みんなの日本語中級Ⅱ』第13課 今週から中級Ⅱに入る
4年生 『みんなの日本語中級Ⅱ』第23課 まもなく中級Ⅱが終了する
3 寮の部屋について
1)大学敷地内にあり、授業をする校舎まで250mの距離。
2)部屋(2F エレベーターなし。部屋はメソネット形式)
1F リビング・キッチン・トイレ
(冷蔵庫・電子レンジ・エアコン・ソファーセット・勉強机・テレビ・整理棚)
2F 寝室・シャワールーム・トイレ
(シングルベッド2・衣装ロッカー・アイロン・アイロン台)
Wi-Fi環境良好・洗濯機2台(寮の出入り口脇・利用時間規定あり)・ゴミは分別なし。
寮の部屋は古いが、十分な広さがある。当然不便なことはいくつもある。電気調理器は加熱に時間を要するし、トイレトペーパーは流せない。日当たりもよくない。2ヶ月間で停電が2回(日中に30分程度)あった。それらはブルガリアの経済状況や衛生環境水準から容易に想像できることではないだろうか。ある程度の心の準備はやはり必要になってくる。しかし、日々の生活からそれらの問題を上回る何かを得られているはずだと思い生活している。これから冬を迎える。2ヶ月間の印象でしかないのかもしれない。
4 ビザ受領までの期間
7/11 無犯罪証明書申請(県警本部)
7/21 証明書受領 即日、アポスティーユ申請(郵送・外務省)
7/28 アポスティーユ受領
7/29 大使館出頭(渋谷区代々木 ビザ申請・面談・ビザ用写真撮影)
8/25 ビザ発給
8/26 ビザ受領(郵送)
ビザ申請にはいくつか必要な証明書等があるが、ICEAからのアドバイスに沿って、時間のかかるものから随時準備を開始し、間に合わせることができた。大使館出頭時に渡航日が決まっていれば、その日に向けてビザ発給をしてくれるようだ。必要書類は国(昨年はポーランド赴任)ごとに案外違うものなんだなと興味深く感じた。長期旅行保険にはブルガリアの会社の廉価のものがある
12月報告
2023年が始まりました。学生たちはクリスマス休暇に里帰りし、まだその姿を見かけません。
ブルガリアのクリスマスはとても静かなクリスマスでした。教会では次々に訪れた方がローソクを灯し、敬虔な祈りを捧げていました。受付の女性にイコンについて質問すると親切に答えてくださいました。どの教会でも彼女たちは一見不愛想にも見えますが、とても親切です。イコンに描かれた聖人たちの名前やその生涯について、もっと知りたいと思いながら帰途に着きました。
ただ市内中心部に設けられたクリスマスマーケットの一角は特別で、連日賑わいを見せていました。さまざまなものに混じって綿あめとリンゴ飴を見かけました。そして、子どもたちのうれしそうな表情と、はしゃぐ姿は日本と何ら変わることがありませんでした。
今は一年中で一番昼の短い時期を送っていますが、一番短い日でも昼の時間は9時間以上あります。朝は7時半過ぎに日の出を迎え、夕方は5時過ぎまで明るさが残っています。クリスマスから10日間快晴に恵まれました。
1 授業進度の報告
1年 「みんなの日本語」初級Ⅰ 17課
週7時間を4人で担当しています。進度はかなり早いと感じています。毎時間、語彙テストか漢字テストがあり ます。さらに漢字シート・文型練習帳の宿題が課されています。
2年 「みんなの日本語」初級Ⅱ 50課
週5時間。1年生同様、毎時間小テストを実施。宿題には作文練習帳が加わります。出席率・課題提出率はとても良好です。先日は50課終了を学生と喜びあいました。
3年 「みんなの日本語」中級Ⅱ 15課
読解では「翻訳・文法解説」の「Vocabulary」を使いこなせていない学生も見受けられます。語彙については、PowerPointを使って補足説明しています。
聞き取りでは2回聞いても細部での聞き落しがあります。練習を重ねることでポイントをつかみとってほしいし、少しでも達成感を感じてもらえればと考えています。
4年 「日本語中級J501」2課
語彙数が飛躍的に増してきます。抽象語も多く、もっと時間を割いて語彙について説明したいという思いになります。発言やスピーチの際は遠慮したり、照れたりする姿も見られます。しかし4年生は自立心が強く、4年間の成長が感じられます。
授業が週4時間(正確には3.5時間)とゆとりがありましたので、1・2年生の希望者を対象に「会話」の時間を新たに設けました。自己紹介の延長線上のようなことをあれこれ話してもらっています。
授業では見られない一面が見られたりしますし、懸命にことばや文型を探しならの会話に声援を送りたい気持ちにさせられます。参加者が少ない時もあります。
2 その他の活動
1 3月予定の文化祭に向けて、11月下旬から書道グループが活動を開始しました。道具はさまざま揃っています。今は動画を見ながら「水書き練習シート」を使って基本練習中です。当初4名でしたが、7名にまで増えました。ここでも4年生がリーダーシップを発揮してくれグループにまとまりがで出てきました。和気あいあいとした活動です。
2 4年生「文学」の授業に加わり、「中古の物語文学」についてプレゼンテーションを行いました。学生は既に「竹取物語」「伊勢物語」「宇津保物語」と「和歌」を学習していました。当時の女性作家(女房たち)を取り巻く環境と時代背景を中心に、彼女たちの作家としての苦心の跡が作品から読み取れることをお話しました。
次回があるなら,「源氏物語」の人物造形の深さと読者(女房たち)の要請によって作品が書き続けられていった過程を話してみたいなと思っています。
3 日本語センターの蔵書について
蔵書数は7300冊にのぼる。まず、日本語学習テキスト、サブテキスト。日本語関連書籍(文法解説書、会話関連図書、専門的な辞典・事典)など。そして日本文化(伝統的文化・現代的文化の双方)・歴史関連書籍。また文学作品では古典作品、個人全集、さまざまなジャンルの単行本・各社の文庫本が揃っている。文庫本は時代小説がかなり充実している。
日本語初級学習者も読めるようにと絵本、おとぎ話、児童文学作品も用意されている。さらに、新書・専門書も相当数揃っている。これらはレポート、論文執筆を意識しての蔵書である。マンガもかなり充実している。
蔵書の多くは1999年にJICAが東欧(ブルガリア)から撤退した際に譲り受けたものだと伺った。蔵書はすべてデータ管理されているし、JICAからの寄贈書籍にはスタンプが押されているので判別が容易である。この財産がソフィア大学ではなく、当大学に引き継がれたことの意味は大きいと思う。この蔵書数は他都市の大学図書館や公立図書館の蔵書数と比較してもかなり多い。蔵書数が飛躍的に増えた当時を想像してみる。
その後も蔵書数は年を重ねるたびに増えてはいるが、予算面での制約もあることだろう、日本で80年代・90年代に注目された(売れた)作品が多い理由もここにある。
4 生活について
ブルガリアの物価は決して安くはないと感じている。それは平均的所得額をEU圏内諸国のそれと比較したとき、もう少し安くなければならないという意味である。日本でも昨年夏から商品価格が高騰しているが、同じ傾向があちらこちらで確認できる。バス料金は1Lvから1.5Lvに、バニツァは1.5Lvから1.8Lvにというふうに。
生活の中で社会インフラの整備、公共サービス、衛生環境水準での立ち遅れを感じることがしばしばある。けれど、そんなことさえ貴重な体験だと思える心構えは持ち続けたい。
ヴェリコ・タルノヴォの水はおいしい。市内至る所にそのまま飲める湧水(チェシマという水汲み場)がある。水道水も日本人にも抵抗感のないおいしさではないだろうか。電気ポットの内側にカリシウム分が白く付着することもない。
携帯電話に関して、生活の多くは大学内・寮内だからWi-Fi環境に不自由を感じることはない。携帯会社「A1」の「1ヶ月10レバ」プランを月初めに更新手続きしている。店員さんにモバイルネットワークをLTE設定に変更してもらって以来、市内どこでも快適に動いている。
日々の買い物もどのスーパーに何が置いてあるかメモしたりして、手際よく買い物をしている。ここではトルコの料理(味付け)が日常的に食されているようだ。
秋から冬にかけてソフィア。ヴァルナ、ルセを訪れました。ソフィアには首都としての、ヴァルナには黒海の街としての、ルセにはドナウ川の街としての表情が感じられました。朝日、夕日にしてもちょっとした違いを感じるのは、旅行という非日常の中で感性がいつも以上になっているからなんだろうか。いつも旅行はそんな違いを感じさせてくれる経験ができる。
ヴェリコ・タルノヴォの郊外にアルバナシがあります。トルコ統治時代には経済面で特別な優遇を受けた歴史がある。独特の雰囲気を持つ町で、どこか違ったヨーロッパを感じさせてくれる、のんびりとした時間が流れる空間です。アルバナシは部屋の窓からも望めるが、南西向きの斜面にあるので日照時間が長くて羨ましいなと感じながら眺めている。
学生が寮に戻ってきたり授業が再開されるまでは、一日24時間が自分の時間になる贅沢を味わっています。少し忙しいのも嫌いではありませんが、一人暮らしの利点が感じられる生活を味わいます。
2月報告
3月1日は「ババ・マルタ」。春の訪れを待ちつつ、互いの健康と幸せを願う日です。紅白の糸で作られたマルティニツァ(リストバンド・糸人形・タッセルなど)をプレゼントしあいます。街では特設の販売所が並んでいました。足を止めてどれにしようかと選ぶ姿を何度も見かけました。先日は大学玄関でもチャリティー販売が行われていました。それをしばらく手首に結んだり、カバン等に付けています。そして、コウノトリやツバメを見かけたら今度はそれを花の咲いている木の枝に吊るします。学園内のあちらこちらに吊るされている昨年のマルティニツァをよく目にします。ブルガリア独特の伝統「ババ・マルタ」にブルガリアの温かさを感じました。お土産にしようと少し多めに購入しました。
2月第1週には雪が降り10㎝ほどの積もりましたが、日中は好天の日が多くすでに春が来たと感じられるほどの陽気です。朝、窓を開けると薪暖房の匂いが微かにしたり、ゆるやかに立ち上る煙も望めます。
1 授業進度の報告
後期の授業が2/20(月)から始まりました。1月下旬には1年生と4年生だけ前期試験と追試がありました。
1年「みんなの日本語」初級Ⅰ課よりスタート
動詞の辞書形からのスタートでしたが、ウォーミングアップに少し時間が必要でした。久しぶりの授業では「・・できる。・・することができる」を練習しました。なお、前期試験は1/19に、追試は1/31に行いました。
2年「みんなの日本語」中級Ⅰ・1課よりスタート
前期に初級Ⅱが終了しました。気持ちも新たに再スタートです。「みんなの日本語」に加えて「毎日の聞き取り40」も同時に進めていきます。
3年「みんなの日本語」中級Ⅱ16課よりスタート
内容的には「悩んだり・落ち込んだり」の16課ですが、「慰めたり・励ましたり」するフレーズも日常生活では必要です。このような表現すら練習の積み重ねが必要なんですね。
4年「アカデミック・エッセイ」を担当します。
後期の試験科目に「アカデミック・エッセイ」があります。その時に「パラグラフ・ライティング」のスタイルで文章が書けることを目標に指導していきます。
後期も1年生の希望者を対象に「会話」の時間を設けました。学生の時間割は個々の専攻(翻訳・ビジネス・観光など)によって異なりますので、時間設定は難しく、結局みんなの空いている時間を見つけることはできませんでした。まず始めることを選択しました。
2 その他の活動
3/18(土)に文化祭が行われます。この文化祭は日本学科単独の開催です。さまざまなグループに分かれて現在準備が進行中です。浴衣の着付け、書道、折り鶴、アニメ・マンガ、日本音楽、食品販売(寿司・ラーメン)日本のおもちゃ展示と内容は豊富です。中には複数グループに所属している意欲的な学生もいます。多くの方の来場が楽しみです。
3「初雪おめでとう」についての私見
ブルガリアでは初雪が降ると「初雪おめでとう」とあいさつします。私はこのあいさつに多少の違和感と興味を感じました。そこでまず学生に尋ねてみました。雪を歓迎する学生は、純粋に雪景色を美しいと感じるからとその理由を教えてくれました。
私の故郷の新潟では初雪は憂鬱な季節の到来と歓迎されないことが多いと思います。長い間人々は雪との闘いを繰り返してきましたし、そして、幾たびも雪害に見舞われてきました。ですから「雪なんか大嫌いだ」が多数派でも仕方ないのかもしれません。
そこでどのような経緯でこのあいさつが定着していったのか考えてみたのです。
まず、初雪は農作業からの解放を意味したのではないでしょうか。前時代の主要産業は言うまでもなく農業です。多くの農業従事者にとって初雪は公然と体を休めることができる季節の到来を意味したのではないかと考えました。「ゆっくり体を休めよう」が「おめでとう」なのではないでしょうか。
また、初雪は敵の襲来がない季節を意味したのではないでしょうか。ご存じのように歴史は戦争で埋め尽くされています。日々敵の襲来を意識しながらの生活だったのだろうと想像します。しかし、雪が降れば雪が自然の守りとなり、敵の進軍を押し止めてくれたのではないでしょうか。しばらく戦争がないことが「初雪おめでとう」に繋がっていったのではと考えました。
4 生活
寮の部屋の窓は北向きです。ところが先日来、朝の時間帯だけ(一時間ほど)陽が差し込むようになりました。日の出の位置の移動が思わぬ恵みをもたらしてくれました。ささやかな喜びです。
また、この春退職を迎える友人が訪ねて来たいとの連絡が来ました。もちろん大歓迎ですと返信しました。帰りの新幹線の時間を気にしながら話すことが多かったことを考えると、ブルガリアでゆっくり話しができることに不思議な感覚を覚えます。コロナ禍による制限もほとんど緩和されたので、きっとスムーズに出入国できるだろうと期待しています。ブルガリアの名所を案内したり、今の生活を見てもらうこを楽しみにしています。
私はこんなふうに日々を送り、春の訪れを待っています。
4月報告
夜明け前から心地よい鳥の声が聞こえてきます。窓を少し開けて甲高く澄んだその声を招き入れます。
きっと南からの渡り鳥でしょう。体はスズメ大ほどでしかないのに、ずいぶん大きな声で鳴くものだと感心しています。ポーランド、ポズナニでも似たような声は聞こえていましたが、あちらはカケスの一種で中型の鳥でした。全身を使い懸命に鳴く姿を見ていると、その名前を知りたい思いになるのは、どことなく親しみを感じているからでしょう。Googleやそれ専用のアプリを活用すれば、何とか答えにたどり着けるのでしょうが今回はまだ成功していません。
また、日の出の位置が北に移動したことで、部屋に朝陽が差し込むようになりました。日の出直後は部屋を貫くように差し込みます。
スベタ・グラの丘に続く斜面はうっそうとした藪が続きます。日ごとに緑が増してきて春山の佇まいです。
1 授業進度の報告
イースター休暇は14日(金)~18日(火)でした。けれど授業(隔週ごとの編成になっている)が少ない週と重なったので、休暇は12日(火)から始まりました。
1年「みんなの日本語」初級Ⅱ・29課まで終了
「・・ている」「・・てある」「・・ておく」などの文型の習得をめざします。
抽象的な概念、例えば「完了」「状態」「継続」「残念な気持ち」などを説明するときは、Google翻訳の英語とブルガリア語の双方を使い、生徒の反応や表情を見ながら進めています。
反復練習を繰り返す中で、体系的な理解へとつなげられないかと私も必死です。学生の「?」が何とか「!」になることを目標に進めています。
2年「みんなの日本語」中級Ⅰ・7課まで終了
イースター休暇中に課題を課しました。「日本語・日本文化との出会い」「日本語の難しさ」「ブルガリア新情報」「授業への要望」について書いてもらいました。
休暇明けの授業でほぼ全員が提出したことはうれしく思いました。そして、日本語のどんなことに難しさを感じていたり、授業内容・進め方にどんな希望を持っているのかを教えてもらえたことは大きな収穫でした。
また、「ブルガリア新情報」は読んでいて楽しいものばかりで、さっそくインターネットで地名・有名人・習慣・料理などを検索しました。
「文法」の時間には学生の苦手意識が伝わってきます。けれど、体系的な理解ができれば苦手意識を少しでも克服する助けになるだろうと思っています。『日本語文法ハンドブック(初級・中上級)』『日本語文法と教え方のポイント(初級・中上級)』の該当箇所を紹介しながら進めています。授業後には「やっぱり難しい」と質問の時間が始まります。無理にその場で答えたりせずに、時間があれば日本語センターまで来てもらい、調べ方を教えたり、用語について一緒に考えることにしています。
3年「みんなの日本語」中級Ⅱ21課まで終了
私の担当は「話す・聞く」の領域です。3年生は学習分野が担当教諭ごとにきっちりと分担されています。授業の進め方も一定の形ができていますし、準備も比較的短時間で終えることができるようになっています。
それぞれの課ごとに、生活のいろいろな場面で出てきそうな言い方が紹介されています。例えば、18課では不平を言った後、謝ったり仲直りする流れが紹介されていますし、19課では自分をアピールしたり、さりげなく自慢話をする方法(そしてその注意点も併せて)が紹介されいます。
今更ながらテキストの構成上の工夫になるほどと感心しながら、生活上のスキルに通じるものがここにあると感じています。
3年前まで高校教師をしていた私はしばしば生徒間(クラス内でも部活動内でも)の衝突に接したことを思い出します。生活の場面場面における適切な言い方の習得が間に合っていない現実と向き合うこともしばしばでした。衝突の中には言い方ひとつで回避できたものもあったように思い出します。その都度問題解決のスキル不足を痛感してきました。今、日本の学校現場では人間関係を良好に保つことが大きな課題になっています。
4年「アカデミック・エッセイ」隔週の授業で6時間終えました。
「パラグラフ・ライティング」のスタイルで文章が書けることを目標に指導しています。「総論・本論・結論」の段落構成も定着しつつあります。また、作品の評価は「構成・内容・表記」の三点を軸に行います。添削後に返却するときも「評価表」を添付しているのは、この三点を意識しながら書くことにつながればとの思いからです。
課題テーマが具体的で身近なものであったり、直接経験したことについてはどんどん書けるのですが、テーマが抽象的で、日頃考えていないことについては苦労しているようです。前回の授業では「素材集めのための検索方法」と「キーワードの検索」について演習しました。日頃からキーワードをしっかり蓄積(記憶)しておくことの重要性を力説しています。なぜならキーワードは自分で作り出すことはほぼ不可能だからです。やや誇張ぎみに「ライティングは暗記科目だ」と。
テストでの出来具合が心配にもなりますが、楽しみでもあります。
2 その他の活動
3/18(土)に日本文化祭が行われました。この文化祭は日本学科単独の開催です。
ソフィア大からS先生・T先生も応援に来てくださり、S先生は生け花の実演、T先生は琴の演奏と、格調高く日本文化を紹介してくださいました。講堂内のステージでは日頃の日本語・日本文化の学習成果の発表が行われました。また玄関ホールには、浴衣の着付け、書道、折り鶴、アニメ・マンガ、日本音楽、食品販売(寿司・ラーメン)日本のおもちゃ紹介と内容豊富なブースが並びました。多くの方の来場を得て、大変な盛況ぶりでした。「この学科に入学したい」という高校生の声も聞くことができました。
私にはこれといった技(特技)がないので、事前は書道グループの活動に加わったり、前日は巻きずし作りのアドバイスをしたり、当日は運営の手伝いをしたり・・、ほぼ雑用係でしたが楽しむことができました。
日頃の授業では見ることのできない学生の一面にも触れ、学生たちに今まで以上の親しみや近さを感じています。授業でもいい意味での変化が感じられます。
4/22(土)にはソフィアで日本語弁論大会が行われました。
本校からは1年男子Dさん(初級)と3年女子Aさん(中級)が参加しました。二人は事前準備にも意欲的で、彼らの日本語・日本文化との出会いを深く理解することができました。
二人に共通のテーマは「マンガ」でした。これらはすでに語り尽くされたテーマの一つで、聞く人へ印象は低く、テーマ選びの段階から関わる必要性も感じました。残念ながら入賞等はかないませんでしたが、二人の積極的な姿勢を高く評価しています。また、前日にはセミナーが行われ、国際交流基金のYさんから東欧諸国の日本語教育事情を紹介していただきました。また夜の食事会では参加したみなさん(ソフィア大の先生方・大使館関係者・セミナー参加の先生方)といろいろお話ができて貴重なひと時でした。
3 生活
こちらでの活動も残すところ2か月となりました。授業は6月第1週で終わり、その後は試験期間となります。最後の授業が終わったら、カザンラクのバラ祭りに出かけてきます。何事ものんびりしているブルガリアでは信じられないことですが、ホテルは1月下旬に予約しました。バラ一色のお祭りなんだそうです。伝統的な歌と踊りに触れてきます。
さて、この街の郊外には10を超える修道院があります。列車やバスの利用として紹介されているところもありますが、ウォーキングコースとして紹介されているところもあります。現在5つ尋ねてみました。修道院はどこもこじんまりとしていて、静かな佇まいです。堂内は彩り鮮やかなイコンが描かれていて、独特な雰囲気を醸し出しています。カソリック教会の堂々とした威容とは対極的です。私はこの魅力を理解するのに少し時間を要しましたが、キリスト教の原風景に触れているとの思いに包まれ、身が引き締まる思いがします。
今は日ごとに帰国を意識しだす頃を迎えています。メモ帳の「先生方への質問」「帰国までにすべきこと」「お土産リスト」「引き継ぎ」欄はどんどん書き込みされて増えるばかりです。
とはいえ焦ってみても仕方ないので、一日一日を大切にすることを心がけて生活していきます。